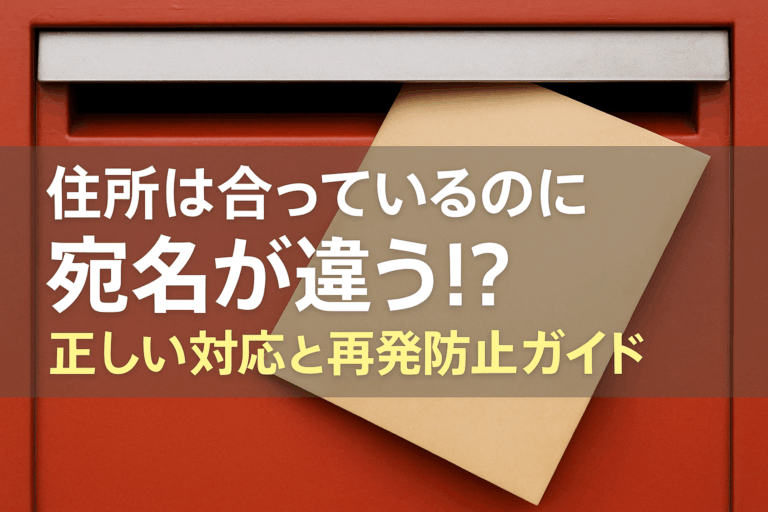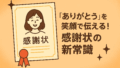ポストを開けたら、自分の住所なのに知らない名前の郵便物――。
そんな経験、ありませんか?一瞬「どうしよう…」と戸惑ってしまいますよね。
実は、「住所は合っているけれど宛名が違う」というトラブルは、引っ越しや入力ミスなど、誰にでも起こりうる身近な問題です。
放置してしまうと、個人情報のトラブルや再配達の手間につながることもあります。
この記事では、宛名が違う郵便や宅配が届いたときに、慌てず安全に対応するための正しい手順をわかりやすく解説します。
さらに、よくあるケース別の対処法や、再発を防ぐためのちょっとした工夫も紹介します。
「これって受け取っていいの?」「誰に連絡すればいい?」と悩んだときに、この記事を読めばスッキリ解決できるように構成しています。
「住所は合っているが宛名が違う!その時どうする?正しい対応と再発防止ガイド」安心して最後まで読んでみてくださいね。
- 1. 「宛名が違うけど住所が合っている」とは?状況整理からスタート
- 2. 届いたときに最初にすべき3つのチェック
- 3. 宛名が違う場合の対応ステップ
- 4. 住所は正しいが宛名が違うときの判断ポイント
- 5. 発送元・業者別の対応まとめ
- 6. 実際のトラブル事例と学び
- 7. 再発防止のためにできること
- 8. トラブルを避けるための知識
- 9. よくある質問(FAQ)
- Q1. 宛名が違っても、住所が合っていれば開けてもいい?
- Q2. 差出人が書かれていない郵便はどうすればいい?
- Q3. 宛名が旧姓や通称名だった場合は受け取ってもいい?
- Q4. 何度も同じ宛名違いの郵便が届くときは?
- Q5. 宛名が違う荷物を宅配ボックスで見つけた場合は?
- Q6. 宅配業者や郵便局に連絡するとき、何を伝えればいい?
- Q7. 誤って開封してしまった場合、法的に問題になる?
- Q8. 「受取拒否」のシールがないときはどうすればいい?
- Q9. 不審な荷物が届いた場合、どこに相談すればいい?
- Q10. 宛名が違う郵便を長期間放置したらどうなる?
- Q11. 他人宛の郵便物を誤って破棄してしまったら?
- Q12. 会社宛の郵便を誤って個人が受け取った場合は?
- Q13. 前の住人の郵便物を毎回返しているのに改善しない場合は?
- Q14. SNSで「宛名違いの郵便が届いた」と投稿してもいい?
- Q15. 「宛名違いの郵便は犯罪です」と脅すような文言を見たけど本当?
- 10. まとめ|落ち着いて、正しい対応をすれば大丈夫
1. 「宛名が違うけど住所が合っている」とは?状況整理からスタート
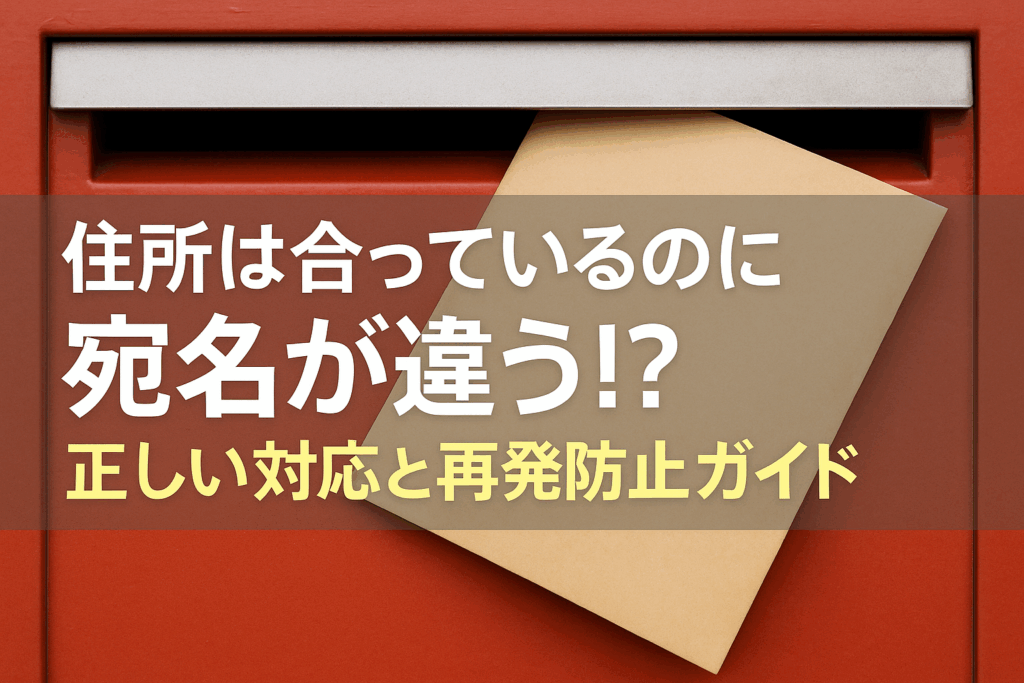
ポストを開けた瞬間、「あれ?住所は自分の家なのに、名前が知らない人になっている…」そんな経験は意外と多くの方がしています。
この「宛名が違うけれど住所が合っている」という状況は、ちょっとした手続きミスや引っ越し後の登録忘れなど、日常の中で簡単に起きてしまうトラブルのひとつです。
まずは、どんなケースが考えられるのかを整理してみましょう。原因を知ることで、落ち着いて正しく対応できるようになります。
よくあるケース①:前の住人宛てに届いた郵便物
最も多いのが、前にその住所に住んでいた人の名前で届くケースです。
引っ越し後に、前の住人が郵便局への「転送届」を出していない場合や、有効期限が切れてしまっている場合に発生します。
この場合は「誤配」ではなく「宛名人が退去後も登録を変更していない」ことが原因。
ポストに入っていても、あなたが開けてしまうと他人宛ての郵便を開封するとトラブルになることがあるため、開けずに連絡するのが安心です。
郵便局へ「この方はもうお住まいではありません」と伝えることで、次からは届かないようにしてもらえます。
よくあるケース②:旧姓・家族・同居人との宛名違い
結婚や離婚、苗字の変更などによって、同じ住所でも宛名が微妙に違うケースもあります。
また、家族や同居人の名前で届く荷物が、あなた宛と勘違いされることもあります。
たとえば、通販サイトや公共料金の登録名が旧姓のままになっていたり、夫婦のどちらかの名前で申し込みをしていた場合などです。
「もしかして家族のものかも?」と思ったら、すぐに開けずに一度確認してからにしましょう。
よくあるケース③:発送元の入力ミス・システム誤登録
インターネット通販や企業からの郵送物では、発送時の宛名登録ミスも珍しくありません。
名前の漢字やフリガナの間違い、別の顧客情報と混ざってしまうなど、システム上のエラーで誤った宛名が印字されることもあります。
この場合は、発送元に「宛名が違っていました」と連絡することで、再発を防げます。
特に、請求書や保証書などの重要書類は、本人確認のための修正手続きが必要になることもあるので、自己判断で処理せずに必ず確認をしましょう。
よくあるケース④:表札やポスト名札が未記入・旧名のまま
意外と多いのが、表札やポストに名前が出ていないケースです。
配達員が「住所は合っているけれど名前が違う」と判断しづらく、結果的に間違った宛名の郵便を投函してしまうことも。
特にマンションや集合住宅では、表札の有無が配達の正確さに大きく関係します。
転居や結婚後は、必ず表札やポストの名前を最新のものにしておくと、こうしたトラブルを防ぐことができます。
よくあるケース⑤:同姓同名・偶然の一致
まれにですが、「同じ名字・同じ番地」に住む別人宛ての郵便が誤って届くこともあります。
特に、アパートや住宅地で同じ苗字の世帯が多い地域では起こりやすいです。
「うちのものかな?」と判断して開けてしまうと、誤開封にあたる可能性があります。
少しでも不安があるときは、宛名・差出人・郵便番号をよく確認して、配送業者や郵便局に相談するのが安心です。
放置してはいけない理由
「自分宛じゃないから…」とそのままにしておくのはNGです。
郵便物や荷物には個人情報が含まれており、誤配送が続くとトラブルの原因になることもあります。
さらに、公共料金の請求書やクレジット関係の通知など、重要な書類が含まれている場合もあるため、宛名違いでも放置せず、正しい手続きを取ることが大切です。
また、繰り返し同じ名前の郵便物が届く場合は、前の住人が転送手続きをしていない、または差出人が情報を更新していない可能性が高いため、郵便局や配送業者に事情を伝えておくとスムーズに解決できます。
まずは状況を落ち着いて整理しよう
宛名が違うと驚いてしまいがちですが、ほとんどのケースは「誰にでも起こり得る小さな手続きミス」です。
大切なのは、慌てて開封したり、放置したりせず、状況を冷静に確認すること。
このあと紹介する「正しい対応ステップ」を知っておけば、次に同じようなことが起きたときにも安心して対処できます。
2. 届いたときに最初にすべき3つのチェック

宛名が違う郵便物や荷物が届いたとき、まず大切なのは「すぐに開けないこと」。
焦って開封してしまうと、思わぬトラブルにつながる場合があります。
ここでは、受け取ったときに確認しておきたい3つのポイントを順に紹介します。
① 差出人を確認する(どこから届いたものかをチェック)
まずは、封筒や伝票に記載された差出人の名前や住所を確認しましょう。
企業名・役所名・学校名などが書かれていれば、どんな内容かおおよそ想像がつきます。
たとえば、
・クレジット会社や銀行 → 重要な個人情報が含まれている可能性
・通販サイト(Amazon、楽天など) → 購入者名の登録ミスかも
・公共機関(市役所・病院など) → 転居や届出に関する通知の可能性
もし知らない企業や個人名だった場合は、その場で無理に判断せず、次の確認ステップに進みましょう。
② 宛名と住所をよく見比べる
次にチェックするのは宛名と住所の両方です。
「住所は自分のものだけど、名前だけ違う」「名前は似ているけど漢字が違う」など、よくあるパターンを確認してみましょう。
もし住所の数字や部屋番号まで完全に一致している場合は、前の住人や家族宛の可能性が高いです。
逆に、住所の一部(丁目や番地)が異なっていれば、配達ミスの可能性も。
どちらの場合も、自分で判断せずに業者へ連絡するのが安心です。
特に、マンションやアパートの場合は部屋番号や表札の確認も忘れずに。
配達員が誤って隣室に届けた郵便を、間違って自分が受け取ってしまうケースも珍しくありません。
③ 開封せずに記録を残す(スマホで撮影がおすすめ)
最後に行いたいのが、受け取った時点での記録です。
封筒や伝票の表面をスマホで撮影しておくと、後から郵便局や宅配業者に連絡するときにスムーズです。
撮影時のポイントは以下の通りです:
- 宛名・住所・差出人が分かるように全体を撮る
- 開封前の状態を残す(封が閉じたまま)
- 個人情報が映らないよう注意して保存する
「もしかして大切な書類かも」と思っても、勝手に開けるのはNGです。
郵便物を開封する行為は、法律上「他人の信書を開けた」とみなされることがあり、トラブルの原因にもなります。
開けずに記録を残し、正しい連絡先(郵便局や配送業者など)に相談すれば、安心して処理が進められます。
ちょっとしたコツ:開封しないまま“保管スペース”を作っておく
「これ、どうすればいいのかな…」と迷った郵便物を一時的に置いておける専用の保管スペースを作っておくと便利です。
たとえば、ポストの横に小さなボックスを置いて「要確認」とラベルを貼っておくだけでもOK。
日常的に郵便物を整理する習慣をつけておくことで、誤配送や宛名違いの対応も落ち着いて行えます。
特に家族と共有しているポストなら、「不明な郵便はここへ置く」とルールを決めておくと安心です。
この3つのチェックを行うだけで、宛名違いの郵便物を正しく見分け、誤った対応を防ぐことができます。
次の章では、実際に「宛名が違っていた場合にどう行動すべきか」を詳しく見ていきましょう。
3. 宛名が違う場合の対応ステップ

宛名が自分と違っていたとき、「どうしたらいいの?」と迷う方は多いですよね。
でも大丈夫。落ち着いて正しい手順を踏めば、トラブルを防ぎながらスムーズに解決できます。
ここでは、郵便物・宅配便・通販サイトなど、さまざまなケースに対応できる基本ステップを紹介します。
① 開封せずにそのまま保管する
まず何より大切なのは、開封しないことです。
「中を見て誰宛かわかればいいのに…」と思うかもしれませんが、他人宛ての郵便は開封せず、まずは郵便局や配達業者へ連絡するのが安心です。
特に「信書(手紙・請求書・契約書など)」の場合は、開封すると郵便法に触れる可能性もあるので要注意です。
届いた状態のまま保管し、次のステップへ進みましょう。
② 配送業者・郵便局に連絡する
次に行うのは、配達を行った業者への連絡です。
封筒や伝票には、どの会社が配送したかが必ず記載されています。
代表的な連絡先は次の通りです:
- 日本郵便:最寄りの郵便局へ持ち込み、窓口で「宛名が違う郵便が届いた」と伝える
- ヤマト運輸:伝票に記載の「営業所番号」や「お問い合わせ番号」でカスタマーサービスへ
- 佐川急便:公式サイトまたは最寄りの営業所へ電話で連絡
- Amazonや楽天などの通販:注文履歴またはお問い合わせフォームから報告
宛名や差出人を伝えると、業者側で「誤配」「宛先違い」として回収・再配達の手続きを行ってくれます。
このとき、撮影しておいた封筒の写真があるとスムーズに話が進みます。
③ 封筒や荷物に「受取人違い」とメモして返送する
郵便局や宅配業者にすぐ行けない場合は、封筒や荷物の表に軽くメモをして返送する方法もあります。
付箋や紙片に「宛名違いのためお返しします」と書いて貼り、ポストへ投函して返送をお願いする方法もあります。心配な場合は窓口に持ち込むと確実です。
たとえば、以下のように書くと丁寧です:
宛名が異なるため返送いたします。
お手数ですがご確認をお願いいたします。
このときも、封を開けずにそのまま返送することがポイントです。
もし封筒に差出人が書かれていない場合は、郵便局に持ち込んで「宛名が違う」と伝えましょう。
スタッフが適切に処理してくれます。
④ 配送業者が来たらその場で説明する
宅配便の場合、配達員さんが再配達や回収に来てくれることもあります。
その際は、封筒や荷物を手渡しながら、「宛名が違っていたため、開けずに保管していました」と一言伝えると丁寧です。
配達員さんは慣れていますので、事情を話せばすぐに持ち帰ってくれます。
このとき、サインや受領印を求められる場合もありますが、宛名が違うときは「受取人ではないためサインできません」と伝えれば大丈夫です。
⑤ 差出人に直接連絡する(重要書類・企業宛の場合)
もし差出人が明記されていて、内容が企業や学校、役所などからの重要なものであれば、直接差出人に連絡するのが確実です。
たとえば、企業名が印字された請求書や通知書の場合、差出人の代表番号や公式サイトに問い合わせフォームが用意されていることが多いです。
「宛名が違う郵送物が届いたので、送り先をご確認ください」と伝えるだけでOK。
こうすることで、差出人側でも住所情報の修正が行われ、再発防止につながります。
⑥ 不安なときは「保留」でもOK
「どこに連絡すればいいかわからない」「差出人が不明で不安…」というときは、無理に動かず一時保管で大丈夫です。
封筒に「宛名違い・確認中」とメモを貼っておき、後日、郵便局にまとめて持ち込むのも安心な方法です。
自分で処理しようとして間違った対応をしてしまうより、専門の窓口に相談することが何より安全です。
ちょっと豆知識:宅配ボックスに入っていた場合
最近は宅配ボックスがある家庭も増えていますが、宛名違いの荷物を勝手に開けたり取り出すのは避けましょう。
管理会社や宅配業者のサポート窓口に連絡すれば、正しい手続きで回収してもらえます。
特にマンションの場合は、管理人さんを通して連絡するのがスムーズです。
このように、宛名違いの郵便物は「開けずに保管 → 連絡 → 返送」の流れを守ることが大切です。
ちょっとした確認でトラブルを防げるので、慌てず一つずつ対処していきましょう。
次の章では、「住所が正しい場合の確認ポイント」について詳しく解説します。
同じようなトラブルを未然に防ぐためのチェック方法を一緒に見ていきましょう。
4. 住所は正しいが宛名が違うときの判断ポイント

「住所は確かに自分のもの。でも、宛名が違う…」という状況は、意外と判断が難しいもの。
特に、同居家族・旧姓・前の住人など、さまざまな可能性が考えられます。
ここでは、そんなときにどこまで自分で判断していいのか、そしてどう行動すれば安全なのかを、やさしく整理していきます。
① 同居人・家族・親族の可能性をチェック
まず考えたいのは、家族や同居人宛ではないかという点です。
たとえば次のようなケースがよくあります:
- 家族がネット通販で旧姓を使って注文していた
- 同居している親や兄弟が、自分の住所で登録している
- 子どもの学校・習い事・資格関係の資料が保護者宛てで届いた
もし家族の名前や関連が思い当たる場合は、本人に確認してから開封すれば問題ありません。
ただし、別世帯の親戚や同居人以外の名義で届いたものは、本人確認を取るまでは開けない方が安全です。
② 旧姓・改姓・通称などの違いを確認
結婚や離婚などで名字が変わったばかりの方は、旧姓のまま登録されている可能性もあります。
通販サイト・公共料金・病院・ポイントカードなど、意外と多くの場面で旧姓のデータが残っています。
この場合は、自分自身宛の郵便物である可能性が高いため、発送元を確認してみましょう。
もし自分の利用しているサービス名や契約先が書かれていれば、宛名に旧姓が残っているだけかもしれません。
また、仕事上の通称(旧姓)を使っている場合もあります。職場・団体・取引先からの郵送物であれば、そのまま受け取って大丈夫です。
③ 前の住人・前の入居者の可能性を確認
引っ越してきて間もない場合は、前の住人宛てであることがよくあります。
郵便局の転送届には有効期限があり、期限切れになると以前の住所宛てに郵便物が届いてしまうのです。
もし心当たりのない名前の場合は、「前の住人あての郵便が届いた」として郵便局に連絡しましょう。
封筒ごと持ち込み、窓口で説明すれば適切に処理してもらえます。
放置してしまうと、前の住人の重要書類や請求書が誤って溜まってしまうこともあるため、早めの対応が大切です。
④ 差出人情報を見て内容を推測する
宛名が違っていても、差出人がわかれば内容の見当がつくことがあります。
たとえば、封筒や伝票に印字された以下のような情報をチェックしましょう:
- 企業名・病院名・役所名など(どの分野からの郵送か)
- 郵便番号や支店名(発送地域から判断できる)
- 「重要」「請求書」「お知らせ」などの記載
この情報をもとに、自分宛か他人宛かを冷静に判断できます。
もし差出人が不明・不安な場合は、開けずに業者または郵便局に確認するのが確実です。
⑤ 個人情報保護の観点から注意すべきこと
誤配の郵便物には、他人の個人情報(氏名・住所・契約内容など)が含まれている場合があります。
たとえ悪意がなくても、勝手に開けたり、SNSなどに写真を投稿するのは避けましょう。思わぬ情報の特定につながることがあります。
また、誤って開封してしまった場合は、そのまま放置せず、郵便局や差出人に正直に連絡しましょう。
事情を説明すれば、適切な手順で処理してもらえます。自分が不利になることはほとんどありません。
大切なのは、「自分のものではない可能性がある」と思った時点で開けないこと。
少しの注意で、トラブルや誤解を未然に防ぐことができます。
⑥ 判断に迷ったときは専門機関に相談を
差出人も不明、心当たりもない、でも住所は自分のもの…。
そんなときは、郵便局や消費生活センターに相談しましょう。
郵便物であれば、郵便局が正式に「誤配処理」をしてくれますし、
通販や民間業者からのものであれば、消費生活センターがアドバイスをしてくれます。
慌てて判断せず、専門の窓口に頼ることが、いちばん安全で確実な方法です。
住所が合っているからといって、必ずしも自分宛とは限りません。
けれど、この記事のポイントを押さえておけば、どんなケースでも落ち着いて対応できます。
次の章では、具体的に「発送業者別の対応方法」や「連絡の仕方」について詳しく紹介していきます。
5. 発送元・業者別の対応まとめ

宛名が違う郵便物や荷物を受け取ってしまったときは、「どの業者が届けたか」によって対応の仕方が変わります。
ここでは、日本郵便・ヤマト運輸・佐川急便・Amazon・楽天などの通販サイト、さらに公的機関や学校など、発送元別に正しい対処法を詳しく紹介します。
それぞれの窓口や手続きの流れを知っておくと、慌てずにスムーズに対応できます。
① 日本郵便(郵便物・ゆうパック・書留など)の場合
日本郵便で届いた郵便物は、封筒や伝票に「〒マーク」や「JP POST」のロゴが入っているのが目印です。
もし宛名が違っている場合は、最寄りの郵便局にそのまま持ち込みましょう。
窓口で「宛名が違う郵便が届きました」と伝えると、職員が内容を確認し、「誤配」または「転送期限切れ」などの処理を行ってくれます。
開封していない状態であれば、特に問題なく引き取ってもらえます。
自宅から出にくい場合は、ポストへの返送も可能です。封筒の表面に付箋などで次のように書き添えてください:
宛名が違うため返送します。
この住所の方は現在お住まいではありません。
このメモを貼ってポストに投函すれば、郵便局が回収して適切に処理してくれます。
また、誤配が頻発している場合は、郵便局に事情を伝えると、配達員へ共有してもらえるので再発防止につながります。
② ヤマト運輸(宅急便)の場合
黒い猫のマークでおなじみのヤマト運輸は、宅配便・ネコポスなど多様な配送を行っています。
宛名が違う荷物が届いた場合は、すぐにヤマトのサービスセンターまたは営業所へ連絡しましょう。
伝票番号(12桁または11桁)が荷物に印字されていますので、電話で「宛名が違う荷物が届いた」と伝えればOK。
オペレーターまたは担当ドライバーが再配達や回収に来てくれます。
ヤマトの連絡先は以下の通りです:
- 固定電話から:0120-01-9625
- 携帯・スマホから:0570-200-000
- 受付時間:8:00~21:00(年中無休)
電話が難しい場合は、ヤマト運輸の公式サイトからも「お問い合わせフォーム」で報告可能です。
ドライバーが自宅に来る場合は、「宛名が違っていたので開封していません」と伝えるだけでOKです。
③ 佐川急便の場合
青いロゴが目印の佐川急便も、全国的に利用者が多い配送業者です。
佐川の場合も、最寄りの営業所または問い合わせ窓口に連絡するのが基本です。
荷物の伝票番号(12桁程度)を伝えると、担当エリアの配達員に引き取り依頼をしてくれます。
宛名違いが確認されれば、差出人に返送される仕組みです。
佐川急便の公式サイトにも「配達に関するお問い合わせフォーム」があり、写真を添付して説明することもできます。
受け取った状態をスマホで撮っておけば、説明がスムーズに進みます。
また、営業所に直接荷物を持ち込む場合は、受付で「宛名が違っていた」と伝えれば、すぐに対応してもらえます。
④ Amazon・楽天・Yahoo!などの通販サイトの場合
通販サイト経由で届いた荷物の場合、発送元は販売店や倉庫であることが多いため、連絡先が少し分かりづらいこともあります。
もし宛名が違っていても、Amazonや楽天などの大手サイトでは、公式サポートから簡単に報告ができます。
- Amazonの場合:注文履歴 → 対象の注文 → 「商品に問題がある」→「誤配送」
- 楽天市場の場合:購入履歴 → ショップへの問い合わせ → 「宛名違いで届いた」と入力
- Yahoo!ショッピング:注文履歴 → ストア問い合わせフォームから報告
もし自分のアカウントに心当たりのない注文が表示されていない場合は、完全な誤配送の可能性が高いです。
開封せずに、Amazonや販売店のカスタマーサービスへ連絡すれば、回収の手配をしてもらえます。
また、Amazonの「置き配」などで玄関先に誤って置かれていた場合も、勝手に開けずに写真を撮り、カスタマーサービスにチャットで報告すると対応が早いです。
⑤ 公的機関(市役所・病院・学校など)からの郵便の場合
役所・病院・学校などからの郵便物は、特に慎重に扱う必要があります。
これらには、個人情報や行政手続きに関する重要な書類が含まれている場合が多いからです。
このような場合は、開けずにすぐ差出人の機関に連絡しましょう。
封筒に記載されている代表番号に電話をして、「宛名が違う郵便が届いた」と伝えるだけで構いません。
担当部署で内容を確認した上で、回収や再送などの対応をしてくれます。
この際、封筒の表面に「開封していない」「宛名が違う」ことを明記しておくと親切です。
病院や学校からの郵送物の場合は、窓口に直接持ち込んでもOK。
本人確認を求められた場合は、事情を説明すれば問題ありません。
⑥ 企業・会社宛てや個人事業主宛てのケース
自宅兼オフィスなどで仕事をしている方は、会社宛てと個人宛てが混在することがあります。
会社名が書かれている郵便物は、基本的に事業主または法人宛のものです。
もし会社名は合っているのに担当者名だけ違う場合は、差出人へ確認するのがベストです。
企業間の書類や請求書の場合は、担当者変更や名義更新がうまく反映されていないだけのこともあります。
また、個人事業主やフリーランスの方で、屋号名・旧社名・旧担当名が残っている場合も多いです。
今後の誤配を防ぐために、取引先や登録サイトの住所情報を定期的に見直すことをおすすめします。
⑦ 差出人が不明・業者の印字がない場合
封筒や荷物に差出人の記載がない場合は、一切開けずに郵便局または配達業者に相談しましょう。
差出人不明のまま放置してしまうと、重要書類や誤配送が繰り返される可能性があります。
郵便局では、「差出人不明郵便物」として正式に扱い、保管・返送などの対応をしてくれます。
宅配業者の場合は、伝票番号から差出人を特定してもらうことが可能です。
とくに、不審な差出人・内容不明の荷物が続く場合は、不安な場合は、消費生活センター(188)や警察相談ダイヤル(#9110)に相談すると状況に合った案内を受けられます。
このように、業者ごとに対応手順は少しずつ違いますが、共通して言えることは、「開封しない」「業者に連絡」「写真を残す」の3ステップです。
この基本さえ守れば、誤配トラブルの多くは安心して解決できます。
次の章では、実際に起こった「トラブル事例とその対応」について、リアルなケースを紹介していきます。
6. 実際のトラブル事例と学び

宛名が違う郵便物や荷物は、誰にでも起こりうる身近なトラブルです。
ここでは、実際にあったケースをもとに、どんな対応をしたらスムーズに解決できたのか、また、どんな点に注意すべきだったのかを具体的に紹介します。
リアルな体験談を知ることで、万が一同じようなことが起きたときにも落ち着いて行動できるようになります。
事例①:前の住人宛ての郵便が毎月届く
引っ越しして半年ほど経ったある女性のもとに、見知らぬ名前の郵便物が定期的に届くようになりました。
最初は「たまたまかな?」とそのまま放置していたそうですが、次第に請求書のような封筒も混ざるようになり、不安を感じるようになったそうです。
郵便局に相談したところ、前の住人が転送届を出していなかったことが原因と判明。
「この方は現在お住まいではありません」とメモを貼って返送したところ、それ以降は届かなくなりました。
学びポイント:
前の住人宛の郵便が届いた場合は、放置せずに郵便局へ伝えるのが最善。
定期的に届くようなら、配達員や窓口に「以前の居住者の郵便が続いている」と伝えると、局内で共有され、再発を防げます。
事例②:通販サイトで注文した商品が他人宛で届いた
ある主婦の方がネットで注文した雑貨が届いたとき、箱に書かれていた名前がまったく知らない人のものでした。
住所は合っているのに宛名だけ違っていたため、間違って自分のものが届いたのか、他人のものが届いたのか判断できずに戸惑ったそうです。
Amazonのカスタマーセンターに連絡すると、「システムの宛名登録ミス」が原因であることが判明。
すぐに業者が回収に来て、正しい商品が再送されました。
学びポイント:
通販トラブルの多くは発送システム上の単純なミス。
「開ける前に写真を撮って連絡」することで、証拠が残り、スムーズに対応してもらえます。
また、同じ商品を再送してもらう際にトラブルを避けるためにも、宛名・注文履歴・伝票番号を控えておくのがおすすめです。
事例③:誤って開封してしまったときの対応
ある男性は、宛名の名字が自分と同じだったため、自分宛だと思い込み郵便物を開封してしまいました。
中を見ると、全く知らない人の契約書。焦って郵便局に持ち込んだところ、
「すぐに届けていただいたので問題ありません」と感謝され、特に大きなトラブルにはならなかったそうです。
学びポイント:
うっかり開封してしまっても、すぐに正直に報告すれば大丈夫。
そのまま隠してしまうと、万が一トラブルが起きたときに説明が難しくなります。
誠実に行動することで、むしろ丁寧な印象を持たれることもあります。
事例④:宅配ボックスに他人宛ての荷物が入っていた
マンションの宅配ボックスを確認したところ、自分の部屋番号のボックスに、他の人の名前が書かれた荷物が入っていたというケース。
受け取るべきか迷ったものの、管理人を通して宅配業者に連絡したところ、配達ミスだったことが判明しました。
後日、業者が回収に来て解決したそうです。
学びポイント:
宅配ボックスの場合は、勝手に開けたり取り出したりしないことが鉄則。
誤配送は業者側の責任になるため、管理会社または配達業者に報告すれば対応してくれます。
開封してしまうとトラブルの原因になりかねないので、落ち着いて手続きを待ちましょう。
事例⑤:会社宛ての郵便物を誤って受け取った
自宅兼オフィスの方に届いた郵便物が、同住所の別会社宛てだったというケースもあります。
住所が同じで社名が似ていたため、配達員が誤って投函してしまったとのこと。
受け取った方は、封を開けずにそのまま郵便局に持参し、事情を説明。
その後、正しい宛先へ再配達され、特にトラブルにはならなかったそうです。
学びポイント:
事業所や会社宛ての郵便は、書類の重要度が高いため、自己判断せず専門窓口へ。
特に契約書・請求書などの可能性がある場合は、慎重な対応が求められます。
事例⑥:同じ名字で誤配が起きた家庭
アパート内で同じ名字の家庭があり、配達員が誤って別世帯の郵便を入れてしまったケースです。
宛名も住所も似ていたため、受け取った側が気づくまでに数日かかりました。
最終的に、郵便局が直接訪問して謝罪・回収し、再配達されました。
学びポイント:
集合住宅や同姓世帯が多い地域では、表札・ポストのフルネーム表記が有効です。
「名字だけの表札」だと誤配が起きやすいため、名前を明記することで防げるケースが多いです。
事例⑦:不審な荷物が届いたときの対処
ある女性のもとに、身に覚えのない荷物が届きました。
宛名は似ているけれど微妙に違い、差出人も不明。中が気になりつつも開けずに、宅配業者に連絡したところ、いたずら配送(いわゆる“ブラッシング詐欺”)であることが判明。
業者がすぐに回収し、個人情報漏えいの被害も防ぐことができました。
学びポイント:
差出人が不明・中身が不明な荷物は、絶対に開けないこと。
中には個人情報を収集する悪質な手口もあるため、業者や警察に相談するのが安全です。
事例⑧:誤配送が繰り返されていたケース
同じ住所に何度も他人の郵便物が届くケースでは、配達ルートやシステム登録に問題がある場合もあります。
ある家庭では、数か月にわたって他人宛ての郵便が届いており、最終的に郵便局が配達エリアの確認を行って改善されました。
学びポイント:
同じようなトラブルが繰り返される場合は、郵便局や業者に「継続して誤配がある」と伝えることが重要。
担当者がルートを再確認し、システムの誤登録を修正してくれます。
一度きりの対応で終わらせず、再発防止の依頼をすることで根本解決につながります。
まとめ:トラブルから学ぶ共通点
これらの事例を通して分かるのは、「開けない・記録を残す・すぐ連絡する」という3つの行動が、どんなケースでも共通して大切だということ。
- 開封せず、まずは封筒・伝票を撮影しておく
- 業者・郵便局・差出人に早めに連絡
- 不安なときは自分で判断せず専門機関に相談
たとえ小さな出来事でも、対応を誤るとトラブルに発展することもあります。
でも、今回紹介したような対応を知っておけば、どんな状況でも落ち着いて行動できるはずです。
次の章では、こうしたトラブルを未然に防ぐためにできる「再発防止策」について詳しく紹介します。
7. 再発防止のためにできること

宛名違いの郵便や荷物が届くと、気づかないうちにストレスになりますよね。
一度対応しても、また同じことが起きると「どうして何度も?」と不安になる方も多いでしょう。
でも大丈夫です。いくつかの対策をしておくだけで、誤配や宛名違いのトラブルはぐっと減らせます。
ここでは、日常の中でできる再発防止の工夫を、具体的に紹介します。
① 引っ越し後は必ず「転送届」を出す
引っ越しをしたら、まず最初にやっておきたいのが郵便局の転送届です。
転送届を出しておくと、旧住所に届いた郵便物を1年間、新住所へ無料で転送してもらえます。
届出の方法は2通り:
- 郵便局の窓口で「転居届」を記入して提出
- 日本郵便の公式サイト「e転居」からオンライン申請
転送期間が切れると旧住所に再び郵便が届くようになるため、期限が切れる前に再申請しておくのがおすすめです。
また、前の住人が転送届を出していない場合は、配達員に「前の住人宛ての郵便が届いています」と伝えることで、再配達を防げます。
② 表札・ポストの名前を最新のものにする
意外と多いのが、表札やポストの名前が古いままというケース。
結婚や離婚、転居後に名前を変更した場合、配達員が判断を誤りやすくなります。
たとえば「旧姓のまま」「名字のみ」「名前なし」といった表札だと、同じ姓の人と間違えて投函されることもあります。
対策としては:
- 名字+名前をフルネームで表記する
- 旧姓を併記する場合は、はっきり分かるように書く(例:山田〈旧姓:佐藤〉)
- ポストと玄関の両方に、統一した表記をする
特にマンションやアパートなど集合住宅では、表札の有無が配達精度に大きく影響します。
「名前が書かれている=本人確認がしやすい」となり、誤配送のリスクを減らせます。
③ 通販サイトや契約サービスの登録情報を見直す
Amazonや楽天、公共料金、携帯会社など、さまざまなサービスで住所登録をしていますよね。
実は、これらの登録住所や名前が古いままになっていることが、宛名違いの原因になることも。
特に、結婚・転職・引っ越しのタイミングでは、以下の情報をまとめて見直しましょう:
- 通販サイトの配送先住所
- クレジットカードや銀行の登録住所
- 電気・ガス・水道などの公共料金契約
- 携帯電話・保険・サブスク契約など
登録情報を最新にしておくことで、誤送付や個人情報の混乱を防げます。
スマホのメモやエクセルなどに「住所変更チェックリスト」を作っておくと、引っ越し時にも役立ちます。
④ 配達業者への共有メモを活用する
もし特定の業者から何度も誤配送がある場合は、配達員への共有メモを活用しましょう。
ポストやドア付近に小さく貼っておくことで、配達員が気づきやすくなります。
たとえば、こんな一言を添えるだけでも効果的です:
宛名「〇〇様」はこの住所にお住まいではありません。
お手数ですがお戻しください。
このように書いておくと、配達員が誤って投函することを防ぎやすくなります。
長期的なトラブル防止に有効な小さな工夫です。
⑤ 家族・同居人との情報共有をしておく
家族や同居人が複数いる家庭では、誰宛ての郵便かを共有する習慣が大切です。
特に子どもが学校や習い事、資格関係などで郵便を受け取ることがある場合は、宛名が似ている郵便が混ざりやすくなります。
対策として:
- リビングなどに「未確認の郵便置き場」を作る
- 「宛名違いのものは勝手に開けない」というルールを共有
- 家族の名前と住所を一覧にして、似ている宛名を把握しておく
家庭内で「誤配・宛名違いの対処ルール」を決めておくことで、混乱を防ぎ、家族全員が安心して対応できます。
⑥ 定期的に「郵便・宅配の届き方」を見直す
近年は、宅配ボックスや置き配などの便利なサービスが増えた反面、誤配のリスクも増えています。
とくにアパートや集合住宅では、複数の荷物が同時に届くため、自分宛の荷物かどうか確認を怠りがちです。
次のような点を定期的に見直しておくと安心です:
- 宅配ボックスに届いた荷物は、宛名・部屋番号を必ず確認
- 置き配場所を限定(玄関前・宅配BOXなど)
- 配達完了メールを確認して間違いがないかチェック
定期的に届き方をチェックしておくことで、「前も同じ間違いがあった」というパターンを防げます。
⑦ 近所で同じ名字の世帯がある場合の工夫
同じ名字の家が近くにあると、配達員が混同してしまうことがあります。
そんなときは、表札や郵便受けに「番地+フルネーム」をしっかり明記しておくと効果的です。
また、ポストの位置が隣接している場合は、郵便受けの中に「このポストは〇〇番地の〇〇家です」と書いたメモを貼っておくのもおすすめ。
ちょっとした工夫で、誤配のリスクを大きく下げることができます。
⑧ 長期間の不在時は「配達一時停止サービス」を利用
旅行や出張などで長期間家を空けるときは、郵便局や宅配業者の一時停止サービスを使うのもおすすめです。
留守中に誤配が起きたり、荷物が玄関に放置されるのを防ぐことができます。
日本郵便の場合は「不在時の一時預かり」、ヤマト運輸や佐川急便にも同様のサービスがあります。
期間を設定しておくと、帰宅後にまとめて受け取ることができるため安心です。
防犯面でも効果があり、留守を狙った空き巣対策にもなります。
⑨ SNSなどへの投稿に注意する
「変な荷物が届いた」「誰宛か分からない郵便がきた」など、SNSに投稿する人もいますが、これは個人情報の拡散リスクにつながります。
たとえ宛名を隠しても、住所やバーコード、差出人の一部が写っていると、悪意のある第三者に特定されることがあります。
投稿したことで相手方の個人情報を漏らしてしまう可能性もあるため、SNSで共有するのは控えましょう。
困ったときは、必ず公式窓口・専門機関に相談するのが一番安全です。
⑩ 「確認・記録・報告」の3ステップを習慣に
宛名違いの郵便トラブルを防ぐには、最後に紹介するこの3ステップが基本です。
- 確認:宛名・住所・差出人を毎回チェック
- 記録:誤配があったら封筒を撮影して残す
- 報告:業者・郵便局に速やかに伝える
この3つを意識するだけで、再発のリスクは大きく減ります。
慣れてくると、郵便物を見るだけで「あ、これは違うな」と自然に判断できるようになります。
ちょっとした心がけで、誤配送のトラブルは確実に減らせます。
これから紹介する次の章では、郵便・荷物トラブルに関するよくある質問(FAQ)をまとめています。
実際に読者の方から寄せられる疑問をもとに、安心できる対処法を紹介していきます。
8. トラブルを避けるための知識

宛名が違う郵便物や荷物を受け取ってしまったとき、
「勝手に開けたらダメなの?」「返さなかったらどうなるの?」と迷うことがありますよね。
ここでは、知っておくと安心な法律・個人情報・マナーの基本知識をやさしく解説します。
難しい専門用語は使わず、日常生活で役立つ形に整理していますので、ぜひ参考にしてください。
① 郵便法で定められている「信書の秘密」
郵便物の中には「信書(しんしょ)」と呼ばれる、個人や企業の意思を伝える書類が含まれる場合があります。
たとえば、手紙・請求書・契約書・領収書・役所からの通知などがこれにあたります。
郵便物は宛名の方が受け取るのが原則です。うっかり開けてしまうと行き違いの原因になることもあるため、開封前に郵便局へ相談すると安心です。
とはいえ、うっかり開けてしまった場合は、すぐに郵便局に連絡すれば問題ありません。
正直に「誤って開けてしまいました」と伝えるだけで、丁寧に対応してもらえます。
大切なのは、「開けたまま放置しない」ことです。
② 個人情報を守るための注意点
郵便物や荷物には、宛名だけでなく住所・電話番号・契約番号など、さまざまな個人情報が含まれています。
そのため、誤って届いた郵便を第三者に見せたり、SNSに投稿したりするのは避けましょう。
ちょっとした投稿でも、封筒の一部やバーコードから差出人や宛先が特定されてしまうことがあります。
最近では、「こんな荷物が届いた!」とSNSでシェアする方もいますが、
情報が写り込むことで思わぬトラブルにつながるケースもあります。
誤配に関する情報は、できるだけ業者や郵便局などの公式窓口に連絡するのが安心です。
開封していなくても、封筒や荷札の写真をネットにアップするのは控えましょう。
自分や相手の個人情報を守ることが、トラブル防止につながります。
③ 「受取拒否」や「返送」の扱いについて
宛名が違う場合に、自分で封筒に「受取拒否」と書いて返送する方法もあります。
ただし、「受取拒否」と「宛名違いの返送」は意味が違うので注意が必要です。
- 受取拒否:自分宛ての郵便や不要なダイレクトメールなどを受け取らない意思表示
- 宛名違いの返送:自分以外の人宛ての郵便が届いたときに返す行為
宛名が違う場合は、「受取拒否」よりも「宛名違いのため返送します」と書き添える方が伝わりやすいことがあります。
どちらの場合も封を開けないことが大前提となります。
もし「受取拒否」のシールがない場合は、付箋でも大丈夫です。
手書きでも丁寧な言葉で書くことで、相手側にも誠意が伝わります。
④ 不審な郵便や荷物が届いたときの安全対策
宛名が違ううえに、差出人も不明で中身もわからない――そんな荷物が届いた場合は、慎重な対応が必要です。
開ける前に次の点を確認しましょう:
- 差出人の名前・住所がはっきり書かれているか
- 知らない通販サイトや海外からの発送ではないか
- 伝票番号や問い合わせ先が印字されているか
不審な点がある場合は、開封せずに業者または警察相談窓口に相談しましょう。
「宅配詐欺」や「ブラッシング詐欺」と呼ばれる手口では、勝手に商品を送りつけ、料金を請求するケースもあります。
身に覚えのない荷物は、「確認せずに開けない」が鉄則です。
⑤ 宛名違いを繰り返さないための記録の残し方
誤配や宛名違いが何度も続く場合は、いつ・どの業者から・どんな名前の郵便が届いたかを記録しておくと役立ちます。
メモ帳でもスマホのメモでもOKです。
記録しておくと、再び郵便局や業者に相談する際に、具体的な証拠として活用できます。
「〇月〇日に〇〇会社から誤配がありました」と伝えると、業者側も状況を把握しやすく、迅速に対応してくれます。
また、封筒を撮影する場合は、宛名や差出人以外の部分を隠すなど、個人情報への配慮も忘れずに行いましょう。
⑥トラブルを防ぐ3つの安心ポイント
誤配送のトラブルを避けるために、最後に覚えておきたいのが次の3つの心得です。
- 1. 開けない:自分宛てかどうか確信が持てないときは開けない
- 2. 放置しない:そのまま置いておくと再配達や個人情報流出の原因になる
- 3. 連絡する:郵便局・業者・差出人に早めに報告する
この3つを守っていれば、誤配送や宛名違いのトラブルに巻き込まれることはほとんどありません。
どんなに小さなことでも、「自分で判断せず相談する」ことが一番安全で確実です。
⑦ 安心して生活するための心構え
誤配や宛名違いの郵便物は、決して珍しいことではありません。
それでも、対応を間違えるとトラブルに発展することがあります。
ですが、今日紹介したような知識を知っていれば、慌てず・正しく・穏やかに対応できます。
法律やルールを難しく考えず、「開けない・確認する・正しく返す」この3つを意識しておくだけで十分です。
ほんの少しの注意と誠実な対応が、自分を守るだけでなく、相手の大切な郵便を守ることにもつながります。
安心して日常を過ごすために、今日の知識をぜひ心の片隅に置いておいてくださいね。
次の章では、よくある質問や「こんなときどうすればいい?」という疑問にお答えします。
実際の悩みに近いQ&A形式で、迷いやすいポイントを分かりやすく整理していきます。
9. よくある質問(FAQ)

宛名が違う郵便物や荷物が届いたとき、多くの人が「これってどうしたらいいの?」と悩みます。
ここでは、実際によく寄せられる質問をもとに、安心して行動できるように分かりやすく答えました。
いざというときに役立つ「暮らしのトラブル防止Q&A」として、ブックマークしておくのもおすすめです。
Q1. 宛名が違っても、住所が合っていれば開けてもいい?
いいえ、開けてはいけません。
たとえ住所が自分のものでも、宛名が違う郵便物は他人宛てとみなされます。
「どんな書類か確認したい」と思っても、封を切らずに、まずは郵便局や配達業者に相談するのが安心です。
誤って開けてしまった場合は、すぐに郵便局や配達業者に連絡し、状況を説明すれば大丈夫です。
誠実に対応すればトラブルになることはほとんどありません。
Q2. 差出人が書かれていない郵便はどうすればいい?
差出人が不明な郵便は、そのまま郵便局に持ち込むのが正解です。
窓口で「宛名が違うが差出人不明」と伝えると、郵便局が正式に「差出人不明郵便物」として扱い、保管・返送の手続きをしてくれます。
無理に開けたり、放置してしまうと、個人情報の扱いでトラブルになる可能性があるため注意しましょう。
Q3. 宛名が旧姓や通称名だった場合は受け取ってもいい?
はい。自分の旧姓や通称で届いたものであれば、本人宛てとして受け取ってOKです。
特に結婚・離婚・転職などで名前が変わったばかりの時期は、旧姓で郵便が届くことがよくあります。
ただし、心当たりのない差出人や重要書類の場合は、念のため発送元に確認すると安心です。
今後のためにも、登録情報を新しい名前に更新しておくのがおすすめです。
Q4. 何度も同じ宛名違いの郵便が届くときは?
繰り返し同じ名前の郵便が届く場合は、郵便局や配達業者に「誤配が続いている」と伝えるのが効果的です。
担当配達員やシステム上の住所登録が修正され、改善されることが多いです。
また、封筒に「この方はお住まいではありません」とメモを貼って返送することで、差出人にも情報が伝わり、再発防止につながります。
Q5. 宛名が違う荷物を宅配ボックスで見つけた場合は?
宅配ボックス内の荷物は、勝手に開けたり持ち出したりしてはいけません。
管理会社または宅配業者に連絡し、「宛名が違う荷物が入っていた」と伝えましょう。
業者が正式に回収・再配達を行います。
誤配送のまま受け取ってしまうと、トラブルの原因になるため、必ず専門窓口を通すのが安心です。
Q6. 宅配業者や郵便局に連絡するとき、何を伝えればいい?
以下の情報を伝えると、スムーズに対応してもらえます:
- 宛名(封筒や荷物に書かれている名前)
- 住所(自分の住所と一致していること)
- 差出人の名前または会社名
- 伝票番号(宅配便の場合)
- 届いた日や時間帯
スマホで封筒や伝票の写真を撮っておくと、説明が簡単になります。
電話のほか、メール・チャットなどオンラインでの報告も受け付けている業者が増えています。
Q7. 誤って開封してしまった場合、法的に問題になる?
故意でなければ問題になることはほとんどありません。
ただし、他人の郵便物を故意に開けたり、内容をコピー・撮影したりすると、他人宛ての郵便を故意に開けたり、内容を撮影・利用するのはトラブルの原因になります。誤って開けてしまった場合は、開封のままにせず郵便局へ相談すると安心です。
誤って開けた場合は、すぐに郵便局に持参し、「宛名が違っていました」と伝えるだけで大丈夫です。
職員が正式に処理してくれます。
Q8. 「受取拒否」のシールがないときはどうすればいい?
シールがなくてもOKです。
封筒の空いている部分に、「宛名違いのため返送します」と手書きでメモを添えるだけで十分です。
ポスト投函も可能ですが、心配な場合は郵便局の窓口に持ち込むとより確実です。
丁寧な言葉で書いておくと、差出人にも誠意が伝わり、再発を防ぎやすくなります。
Q9. 不審な荷物が届いた場合、どこに相談すればいい?
差出人不明の荷物や、覚えのない商品が届いた場合は、まず業者に連絡してください。
それでも不安が残るときは、消費生活センター(188)や最寄りの警察相談ダイヤル(#9110)に連絡を。
特に、「代引きで届いた」「開けたら請求書が入っていた」といったケースは、詐欺の可能性があります。
自己判断せず、専門機関に相談するのが安心です。
Q10. 宛名が違う郵便を長期間放置したらどうなる?
放置すると、再配達や個人情報漏えいの原因になる可能性があります。
郵便局や差出人は「届いた」と認識できないため、誤送付が続いてしまうケースもあります。
気づいた時点で「宛名が違うため返送」と書いて返すことで、早期解決につながります。
特に前の住人宛の郵便が頻発する場合は、郵便局に相談しておくと安心です。
Q11. 他人宛の郵便物を誤って破棄してしまったら?
もし誤って処分してしまった場合は、できるだけ早く郵便局へ報告しましょう。
誤配の経緯を説明すれば、状況を記録して今後の配達に活かしてもらえます。
法律上の罰則は「故意」の場合のみ適用されますので、焦らず正直に伝えましょう。
今後は、宛名や差出人を確認してから処分する習慣をつけておくと安心です。
Q12. 会社宛の郵便を誤って個人が受け取った場合は?
会社宛の郵便を誤って受け取ってしまった場合も、開けずに返送するのが基本です。
企業間の契約書や機密資料が含まれている可能性があるため、自分で開封せず、郵便局または差出人に返すようにしましょう。
もし取引先など知っている企業であれば、連絡を入れて「誤って届きました」と伝えるのも親切です。
誠実な対応は信頼にもつながります。
Q13. 前の住人の郵便物を毎回返しているのに改善しない場合は?
繰り返し届く場合は、郵便局の窓口で「前の住人の転送届が切れているかもしれません」と相談しましょう。
配達担当者へ情報共有され、今後の配達ルートで改善されるケースが多いです。
また、封筒に「〇〇様は転居されています」と書いて返送すると、差出人にも情報が伝わり、登録修正を促すことができます。
Q14. SNSで「宛名違いの郵便が届いた」と投稿してもいい?
おすすめしません。
住所や封筒の一部から個人情報が特定される可能性があるため、SNSへの投稿は控えるのが安全です。
「誰かのものが間違って届いた」という内容でも、差出人や宛名が写っていると情報漏えいにつながることがあります。
そのような場合は、投稿よりも業者や郵便局に直接連絡しましょう。
Q15. 「宛名違いの郵便は犯罪です」と脅すような文言を見たけど本当?
誤って届いた郵便を「受け取った」だけでは犯罪にはなりません。
ただし、他人宛ての郵便を故意に開封・破棄・利用した場合は、法律違反になることがあります。
「知らなかった」「つい開けてしまった」という場合は、郵便局に相談すれば大丈夫です。
きちんと報告することで、むしろ誠実な対応として評価されます。
このQ&Aを読んでいただければ、宛名違いのトラブルにも落ち着いて対応できるはずです。
最後の章では、この記事の内容をまとめて、日常生活で役立つ「安心のチェックリスト」として振り返ります。
10. まとめ|落ち着いて、正しい対応をすれば大丈夫

宛名が違う郵便や荷物が届いても、慌てる必要はありません。
大切なのは、「開けない・放置しない・連絡する」の3つを守ること。
住所や宛名を確認して、誤りがあれば郵便局や配達業者に伝えれば、多くのケースでスムーズに解決につながります。
また、転送届の提出や表札の更新、通販サイトの登録見直しなど、日ごろの小さな工夫も再発防止につながります。
SNSへの投稿や自己判断での開封は避けて、正しい窓口に相談することが安心への近道です。
宛名違いの郵便は、誰にでも起こること。
でも、知っていればもう怖くありません。
落ち着いて丁寧に対応すれば、あなたの手で小さなトラブルを穏やかに解決できます。
慌てず・丁寧に・誠実に。
それだけで、暮らしはもっと安心になります。