新幹線での移動中、思わず電話が鳴ってしまったことはありませんか?
ビジネスの緊急連絡や家族からの連絡など、やむを得ず通話をする場面もあるかもしれません。しかし、新幹線は多くの人が利用する公共の場。
たとえ短時間の通話でも、周囲にとっては大きなストレスとなることがあります。
この記事では、快適でトラブルのない車内環境を守るための「電話マナー」について、JR東海の案内や具体的な行動例を交えながら詳しく解説していきます。
通話が必要なとき、どう振る舞えばいいのか。どんな点に気をつければ、まわりに配慮したスマートな対応ができるのか。日常に役立つヒントをお届けします。
新幹線での電話マナーとは?

新幹線の基本的な通話ルール
新幹線では、座席での通話は原則として控えるよう案内されています。
多くの乗客が快適な時間を過ごす空間であるため、大きな声や長時間の会話はトラブルの元になりがちです。
通話が必要な場合には、車両の間にあるデッキや通話可能エリアへ移動し、周囲の迷惑にならないように利用しましょう。
また、着信音を鳴らさないようマナーモードに設定しておくことも基本中の基本です。
イヤホンマイクを使う際も、つい声が大きくならないよう注意が必要です。
迷惑にならないための配慮
周囲の乗客に不快感を与えないためには、ちょっとした配慮が大きな差を生みます。
たとえば、通話時の声のトーンを抑えたり、要点だけを手短に話すようにしたりすることで、印象は大きく変わります。
また、着信があった場合にすぐに出ず、「電車の中なので後ほどかけ直します」と静かに伝えるだけでも、周囲の理解を得やすくなります。
自分が話しているときの周囲の表情や反応を観察しながら行動することも、スマートなマナーといえるでしょう。
どうしても通話が必要なときの対処法
緊急の連絡や仕事の対応など、どうしても電話をかける必要があるときは、できる限り周囲に配慮したうえで行動することが大切です。
まず、静かな場所に移動し、通話が終わったら速やかに席へ戻ること。
また、通話内容がプライバシーに関わるものであれば、第三者に聞かれても問題ないかを事前に考えておく必要があります。
社外秘の情報や家族のプライベートな話題などは、できるだけ移動後に行うなど、判断と行動のバランスが求められます。
電話ができる車両と場所

デッキでの通話とその注意点
車両と車両の間にあるデッキスペースは、新幹線内で通話を行う際の推奨場所です。
比較的静かなスペースであることから、他の乗客に配慮しながら会話をすることができます。
ただし、ここでも注意が必要です。デッキはトイレの出入口やドアの開閉が頻繁にある場所でもあるため、長時間立ち止まると通行の妨げになってしまいます。
また、複数人での会話や声のトーンが大きすぎると、車内に声が漏れることもあるため、静かに短時間で用件を済ませるよう心がけましょう。
トイレで電話をかける場合のマナー
トイレの個室を通話の場所として使うことは、基本的に推奨されていません。
長時間の利用は、トイレを必要としている他の乗客に迷惑がかかるだけでなく、密閉空間では音が反響しやすく、話し声が外に漏れてしまうこともあります。
また、衛生面や空調の問題から、通話に適した環境とはいえません。どうしても通話しなければならない場合でも、トイレを利用するのではなく、デッキや専用の通話スペースを選ぶのがベストです。
優先席付近での電話利用について
優先席エリアでは、ペースメーカーなどの医療機器を使用している方が乗車している可能性があるため、特別な配慮が必要です。
かつては「携帯電話の電源をお切りください」と案内されていましたが、現在でも車内表示やアナウンスによって、携帯電話の利用を控えるよう求められていることがあります。
そのような表示がある場合は、マナーモードではなく、携帯の電源を完全にオフにするのがマナーです。
トラブルや誤作動を未然に防ぐためにも、指示に従いましょう。
周囲への配慮と注意点

うるさいと感じられないための工夫
新幹線内での通話が「うるさい」と感じられるのは、話している側が自分の声量や周囲の空気感に無頓着なことが多いからです。
特にビジネスの話など、感情や熱量がこもりやすい会話は、自然と声が大きくなりがちです。
そのため、通話を始める前に深呼吸して声を落ち着ける、周囲の人の距離を意識する、マスクをつけて声をこもらせるなどの工夫が効果的です。
また、イヤホンマイクを使うことで手ぶらになり、よりリラックスした声のトーンを保ちやすくなる場合もあります。
大切なのは「自分が快適に話すこと」よりも「周囲の人が快適に過ごせること」に意識を向けることです。
電源を切るべき場面とその重要性
一部の車両や座席では、携帯電話の電源を完全に切るよう求められている場合があります。
これは、医療機器との電波干渉を防ぐための大切な措置です。
特にペースメーカーやICD(植え込み型除細動器)などの機器を使用している方が近くにいる可能性がある場所では、マナーモードではなく電源をオフにすることが必要です。
電源を切る場面では、周囲の案内表示やアナウンスにしっかりと従いましょう。
また、意図せず音楽や動画が再生されることを防ぐ意味でも、電源オフは安全策となります。
安心・安全な車内環境を守るためにも、自分自身の端末に対する意識を高めることが求められます。
トラブルを避けるためのルール

禁止事項とその理由
新幹線では、座席での長時間通話、大きな声での会話、通話しながらの車内移動などが明確に禁止されているわけではなくても、マナー違反と見なされがちです。
特に混雑している時間帯や車内が静かなときには、少しの音でも周囲に不快感を与えることがあります。
また、デッキでの通話も占有や大声での使用は避けるべきです。
これらの行為は他の乗客とのトラブルの火種にもなりやすく、場合によっては乗務員から注意を受けることもあります。
すべての乗客が気持ちよく移動できるよう、お互いを思いやる気持ちを持って行動することが求められます。
通話中の注意事項と周囲の反応
通話に集中してしまうと、自分の声量や周囲の状況に気づきにくくなります。
その結果、声が大きくなったり、無意識に身振り手振りを交えて話してしまうこともあります。
こうした行動は、周囲に「配慮が足りない」と受け取られる原因になりかねません。
また、通話中に周囲の人の視線や態度が変わったときは、自分の行動を見直すサインかもしれません。
ときには直接注意を受けたり、SNSなどで苦情を書かれてしまうケースもあるため、自分自身の通話マナーに常に気を配ることが大切です。
新幹線の電話に関するFAQ

よくある質問とその回答
新幹線での通話マナーについては、多くの人が同じような疑問を抱えています。
たとえば「座席での通話は絶対にNGなのか?」「深夜の時間帯なら少し話してもよい?」「小声ならOK?」といった声がよく聞かれます。
基本的な答えとしては、すべての乗客が快適に過ごせる空間であることを前提に、「通話は原則としてデッキなどの指定された場所で」がルールとなります。
深夜や早朝でも、車内が静まり返っていることが多いため、小さな声でも響いてしまう可能性があります。
さらに、ビジネス通話での情報漏洩リスクや、周囲のストレスを増やしてしまう要因になり得ることも覚えておきたいポイントです。
私的利用とビジネス利用の違い
通話の内容によっても、マナーの印象は大きく異なります。
たとえば「今日の晩ご飯どうする?」といった私的な内容は短時間で済むことが多く、周囲の迷惑にもなりにくい傾向があります。
しかし、ビジネス通話では内容が込み入っていたり、相手の声が聞き取りづらくて何度も聞き返す場面があったりと、長時間になりがちです。
また、社外秘の情報や顧客との会話など、機密性の高い内容を周囲に聞かれてしまうリスクもあります。
そうした点からも、ビジネス目的の通話は特に場所選びと声の配慮が必要です。
周囲の人は内容の是非よりも、「この人は周りに配慮しているかどうか」で印象を判断することが多いため、自分本位にならない姿勢が求められます。
JR東海からの電話マナー案内

公式に案内されているルール
JR東海では、車内での通話に関するマナーについて明確なガイドラインを示しています。
東海道新幹線を利用する多くの乗客が快適に過ごせるよう、「車内での通話はデッキなどの専用スペースで行うようにしてください」と繰り返しアナウンスされています。
また、車内ポスターや座席ポケットに挟まれたパンフレットなどにも、携帯電話のマナーに関する情報が掲載されており、利用者への啓発が行われています。
駅構内やホームにも案内表示があり、乗車前からマナーを意識できるような配慮がなされています。
特に混雑時間帯やビジネス利用の多い平日は、静かな空間が求められるため、このルールは重要視されています。
快適な移動のための提案
JR東海をはじめとする鉄道会社は、乗客全員が気持ちよく移動できるように、通話以外の連絡手段の活用も推奨しています。
たとえば、LINEやメール、ビジネスチャットなど、音を出さずに情報をやり取りできるツールを使えば、周囲への迷惑を最小限に抑えることが可能です。
また、通話が必要な場合には、最寄りのデッキや通話スペースに移動することを日頃から意識しておくとスムーズです。
こうしたマナーを守ることで、結果的に自分自身も気兼ねなく新幹線の時間を過ごすことができ、ビジネスでもプライベートでも良い印象を与えることができます。
鉄道会社の案内を活用しながら、ひとりひとりが快適な車内環境づくりに協力していくことが大切です。
まとめ:通話マナーを守って快適な新幹線の旅を
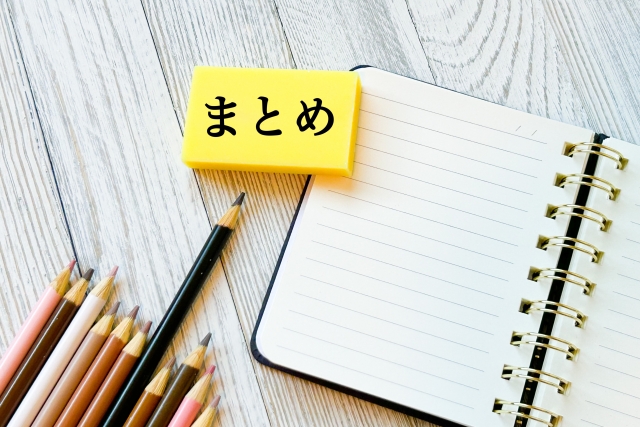
新幹線は多くの人が利用する公共の空間であり、通話ひとつにも思いやりが求められます。
座席での電話は原則として控え、必要な際はデッキなど決められた場所へ移動する、という基本マナーを守るだけで、周囲の人とのトラブルを未然に防ぐことができます。
また、ビジネスやプライベートを問わず、通話中は声のトーンや時間に配慮し、内容が周囲に聞かれて困るものであれば避けるなど、状況判断が重要です。
JR東海の案内や車内の掲示も活用しながら、スマートに行動できると理想的です。
ひとりひとりが少しずつ意識を変えることで、誰もが快適に移動できる環境がつくられます。
マナーは「守る」ものではなく、「思いやる」もの。気持ちの良い新幹線の旅を、すべての人と分かち合いましょう。

