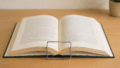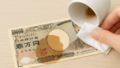毎日ぐっすり眠るために欠かせないマットレス。
でも、ふとシーツを外してみたら 「あれ?うっすら黄ばみ?」 「なんだかムッとした臭い…」 なんて経験はありませんか?
本記事では、ドラッグストアでも100円ショップでも手に入る「重曹」を使って、カビ・黄ばみ・おねしょ汚れまでまるっとお掃除する方法を、初心者さんでも失敗なくできるよう優しく解説します。「もう買い替えしかないかも…」とあきらめる前に、ぜひ読んでみてくださいね♪
最初に確認!カビ・黄ばみ・尿汚れ…そのまま放置していませんか?

カビや黄ばみは
- 寝汗や皮脂がマットレス内部にしみ込む
- 通気不足で湿気がこもる
- おねしょや飲みこぼしをすぐに拭き取らず放置
といった日常の小さな習慣が原因で発生します。
「見えない部分だから大丈夫」と放っておくと、
ダニの温床になったり、アレルギー・においの悪化につながることも…。
まずは次のチェックリストで、今の状態を軽くセルフ診断しましょう。
- シーツを外すとマットレス表面にグレーや黒い点がある
- 寝室に入るたび、湿ったような独特の臭いを感じる
- おねしょ後、応急処置だけで深層まで洗えていない気がする
ひとつでも当てはまったら、今日がリセットのチャンス。これから紹介する重曹ケアをぜひ試してみてくださいね。
重曹って本当に効果あるの?プロ級の理由を科学的に解説
重曹(炭酸水素ナトリウム)は、実は「弱アルカリ性」の性質を持っています。
汗やおねしょの主成分=タンパク質&尿酸は酸性寄り。弱アルカリ性の重曹はこれらを中和して汚れを分解→浮かせる働きがあります。さらに…
- 消臭効果:重曹粒子が臭い分子を吸着し、中和。
- 吸湿効果:微細な多孔質構造が湿気をキャッチ。
- 研磨作用:粒子がやさしく表面の黄ばみをこすり落とす。
しかも食用・医療用にも使われるほど安全性が高いので、小さなお子さんやペットがいるご家庭でも安心。
プロのクリーニング業者さんも、下処理として重曹を活用することが多いんですよ♪
「強い洗剤はちょっと不安…」という方は、まずは重曹からスタートしてみましょう。
重曹で掃除する前に|マットレス掃除の基本と素材別の注意点

「よし、重曹でお掃除しよう!」とやる気満々の方も、ちょっと待ってくださいね。
実はマットレスの種類によって、向いているお手入れ方法と、やってはいけないNGケアがあるんです。
ここでは、まず「自分のマットレスがどんな素材なのか」を確認し、その上で重曹掃除が安全かどうか、他のアイテムとの組み合わせ方を優しく解説していきます。
ウレタン・ポケットコイル・ラテックス…素材ごとのNG&OK
マットレスは一見同じように見えても、中身の構造はまったく違うことがあります。
重曹が使えるかどうかを知るには、まず「素材チェック」が大切。代表的なタイプはこちらです:
- ポケットコイル・ボンネルコイルタイプ:
表面はウレタンや布製のため、基本的に重曹を振りかける方法はOKです。ただし、中のスプリングが湿気を含むとサビやカビの原因になるので、必ずしっかり乾かしましょう。 - ウレタンマットレス(高反発・低反発):
重曹のふりかけ&掃除機吸引はOKですが、水分を含む重曹スプレーは避けた方が安心。ウレタンは吸水性が高く、乾きにくいためカビが生えやすくなります。 - ラテックスマットレス:
天然ゴム素材で通気性が低く、水分を含むと劣化や変色の恐れがあります。重曹スプレーや水洗いはNG。
軽く重曹をふりかけて臭いや湿気を取ったら、早めに掃除機で回収するのがベストです。
なお、取扱説明書やマットレスのタグに「水洗い不可」などの記載がある場合は、それに従ってくださいね。
一見大丈夫そうでも、内部にしみ込むとトラブルの元になることもあるので、素材ごとの特徴をしっかり把握してからスタートしましょう。
重曹スプレー・クエン酸・オキシクリーンの効果と使い分け
重曹だけでもかなり優秀ですが、「他のアイテムと併用したい」という方も多いはず。ここでは、人気のお掃除アイテム3つの特徴と使いどころをご紹介します♪
- 重曹(アルカリ性):
尿や汗などの酸性の汚れに効果抜群。消臭・吸湿・汚れの浮き上がりに強いので、まず最初に試すべきアイテムです。 - クエン酸(酸性):
逆にアルカリ性の汚れ(皮脂・石けんカス)に効果的。
ただし、マットレスには直接使うよりも、空間の消臭や除菌スプレーとして使うのがおすすめ。
布製品にかけすぎると色落ちの心配もあるので、注意してくださいね。 - オキシクリーン(酸素系漂白剤):
黄ばみやしつこいシミに強いパワーを発揮!
ただし素材を痛めるリスクもあるので、薄めてごく一部にだけ使うのが鉄則です。
「どうしても取れない汚れにだけピンポイントで使う」感覚で活用しましょう。
どれも使い方を間違えなければ頼もしい味方になりますが、まずは重曹単体で十分にきれいになることが多いですよ。
やってはいけない掃除法|失敗例とリスク回避のコツ
実際にマットレス掃除でよくある失敗をいくつかご紹介します。
「えっ、私もやってたかも…」というケースもあるかもしれません。
- 重曹スプレーをたっぷり吹きすぎて乾かしきれない
→ 湿気が残ってカビの原因に!
スプレーは軽くひと吹き&しっかり乾燥が基本です。 - お風呂場で水洗いしてしまう
→ 中まで濡れて乾かず、異臭や変形の原因に。
「洗った方がきれいになる」と思っても、マットレスは水洗いNGが基本です。 - ドライヤーを近づけすぎて焦がしてしまう
→ ウレタンや合成繊維が変形・変色する危険あり。
乾燥は陰干し+扇風機・布団乾燥機がおすすめです。
お掃除のつもりが、マットレスの寿命を縮めてしまってはもったいないですよね。
「あくまで部分的に、優しく、しっかり乾かす」が基本です。焦らずゆっくり、安心して作業していきましょう♪
【準備編】必要な道具&事前にやるべきことまとめ

重曹でマットレスをきれいにするには、準備がとっても大切。
使う道具やお掃除の流れをきちんと整えておくだけで、仕上がりがぐんと違ってきますし、作業もスムーズに進みますよ♪
忙しい方でも「1時間だけ集中」などの時短掃除ができるように、事前にしっかり備えておきましょう。
あると便利な道具リスト|重曹・古タオル・掃除機・防水シートなど
まずは、マットレス掃除に使う基本アイテムを揃えましょう。すでにおうちにあるものも多いので、確認してみてくださいね。
- 重曹(粉タイプ)
粉のままふりかけて汚れや臭いを吸着させます。ドラッグストア・100均・スーパーなど、どこでも手に入る便利アイテム♪ - スプレーボトル
重曹水を作るときに使います。できれば細かいミストタイプのノズルが◎。 - 古タオル・いらない布
こぼれた液体を拭き取ったり、軽くたたいて汚れを浮かせるときに使います。濡れてもOKな布がおすすめ。 - 掃除機
ふりかけた重曹を回収するのに使います。紙パック式よりサイクロン式のほうが重曹詰まりしにくいです。 - ゴム手袋
肌が敏感な方は手荒れ防止に。重曹は食品用でも意外と手がカサつくこともあります。 - 防水シート or レジャーシート
フローリングやカーペットの上で掃除する場合、下に敷いておくと汚れや湿気の浸透を防げて安心。 - 布団乾燥機 or 扇風機
掃除後の乾燥に大活躍!特に梅雨時期や冬場は、自然乾燥だけでは足りないこともあるので、風をしっかり当ててあげましょう。
すべて完璧に揃っていなくても大丈夫ですが、「重曹+掃除機+乾かす道具」は最低限あった方が安心ですよ。
掃除前にやるべき下準備|換気・分解・日当たりチェック
道具の準備ができたら、次は「お掃除環境を整える」ステップへ。
ちょっとした工夫で汚れ落ちも乾きもグッと良くなります。
- 窓を開けてしっかり換気
掃除中はホコリや湿気が出やすくなります。
空気の流れを作っておくと乾燥が早まり、カビ予防にもなりますよ。
できれば扇風機やサーキュレーターも併用すると効果UP! - ベッドフレームからマットレスを外す
お掃除しやすくするために、可能であればマットレスを床や広めのスペースに移動しましょう。
ベッドの上だと下に重曹が落ちてしまうこともあるので、レジャーシートなどを床に敷いておくのが◎。 - カバーやパッドは外しておく
表面にシーツやベッドパッドがあると汚れの範囲が見えにくいです。
お掃除前にすべて取り外して、ついでに洗濯もしておくと効率的♪ - 天気や湿度もチェック
雨の日や湿気の多い日は、乾燥が進みにくくカビのリスクが上がります。
できれば晴れの日、または布団乾燥機や扇風機が使える日を選ぶと安心です。
少し手間に感じるかもしれませんが、下準備をしっかりしておくと、掃除の効果がしっかり出て、気持ちよく作業できるようになりますよ。
自分のペースで、できるところからで大丈夫。お掃除を「頑張る日」ではなく、「おうちを整えるやさしい時間」と思ってみてくださいね。
【実践編】重曹を使ったマットレスの掃除手順と汚れ別対策

いよいよお掃除スタートです♪
「やり方が多すぎて迷いそう…」という初心者さんでも、順番通りに進めれば失敗しませんので安心してくださいね。
汚れの種類によってコツが少しずつ変わるので、まずは基本の手順を押さえてから、気になる汚れ別にアレンジしていきましょう。
基本の手順|ふりかけ → 放置 → 掃除機の順でスッキリ
- 粉の重曹をたっぷりふりかける
目安:汚れのある部分+周囲5cmほど
サラサラと雪をかぶせるイメージでOKです。表面がうっすら白くなるくらいがベスト。 - 30分〜1時間放置
重曹が汚れやニオイを吸着&中和してくれる時間です。
晴れていれば日当たりの良い窓辺で、雨の日は換気+扇風機を当てておくとさらに◎。 - ゆっくり掃除機で吸い取る
ノズルを生地にぴたっと沿わせるように当て、重曹をしっかり回収します。
このとき1か所2〜3秒かけるイメージでゆっくり動かすと、粉が残りにくいです。 - 仕上げの乾燥
換気+扇風機/布団乾燥機で風を当て、最後に手で触ってサラッとしていれば完了です。
重曹スプレーやペーストの作り方|濃度と用途の違い
粉だけでは取り切れないシミには、重曹水(スプレー)や重曹ペーストが活躍!作り方はとっても簡単です。
- 重曹スプレー(軽い汚れ・広範囲に◎)
・水200ml+重曹小さじ1(約5g)をスプレーボトルに入れ、よく振って溶かすだけ。
・弱アルカリ性で汗・尿など酸性汚れをゆるめてくれます。
・布がびしょびしょにならないよう、“シュッ”とミスト状に軽く吹きかけるのがコツ。 - 重曹ペースト(部分的なシミ・黄ばみに◎)
・重曹大さじ2+水小さじ1〜2を混ぜて歯磨き粉くらいのかたさに。
・シミの上に厚めに塗り、ラップをのせて15〜30分置いたら布で拭き取り。
・最後に固く絞ったタオルで軽く水拭きし、しっかり乾かしましょう。
おねしょ・血液・汗・皮脂・ペット臭など汚れ別の落とし方
| 汚れの種類 | おすすめアプローチ | ポイント |
|---|---|---|
| おねしょ(尿) | ①重曹スプレーで湿らせ ②ペーストをのせ30分放置 ③粉をふりかけ追加吸着 |
アルカリ臭が残りやすいので酢やクエン酸スプレーで軽く中和→しっかり乾燥 |
| 血液 | ①冷水+重曹ペーストでたたき出す ②酸素系漂白剤を綿棒で少量(色落ちテスト必須) |
温水はタンパク質を固めるのでNG!必ず冷水で。 |
| 寝汗・皮脂 | ①粉重曹を広範囲に振り放置 ②掃除機で吸う→仕上げに重曹スプレーを薄く |
定期ケアでOK。月1回の重曹振りかけ習慣がおすすめ。 |
| ペット臭 | ①粗相をすぐペーパーで吸い取る ②重曹スプレー→ペースト→粉の順 ③最後にアルコール除菌で仕上げ |
臭い戻り防止に風通し&紫外線が効果的。ベランダで陰干し◎ |
どうしても落ちないカビ・黄ばみはこう対処!
- ペースト+ラップ+放置時間を延長
2〜3時間置くことで漂白効果がアップします。 - 酸素系漂白剤を薄めてピンポイント
色柄のあるカバーは目立たない所でテスト必須。 - 日光+布団乾燥機のダブル乾燥
紫外線でカビ菌を不活化し、熱で水分を飛ばすと再発防止に◎。 - それでも無理ならプロへ相談
「黒カビが広範囲」「異臭が取れない」場合は、専門クリーニングや買い替えを検討しましょう。
本体とカバー、どこまで掃除?洗えるもの/洗えないもの
最後に「ここまでOK・ここからNG」を確認しましょう。
- カバー・シーツ・パッド:基本的に洗濯機OK。30〜40℃のぬるま湯+酸素系漂白剤でスッキリ。
- ファスナー付き外カバー(取り外し式):洗濯表示を確認。ウレタン裏地付きは手洗い+陰干しが安心。
- マットレス本体(ウレタン・ラテックス):水洗いNG。
表面の粉重曹+掃除機+風乾でケア。どうしても水分が入ったら、48時間以上乾燥を。 - スプリングタイプの外装生地:薄い汚れなら重曹スプレーOK。
深部まで濡らすとコイルがサビるので浸水厳禁です。
「どこまでやるか迷う…」ときは、洗濯表示&取扱説明書を再チェック。迷ったら粉+掃除機+乾燥が最も安全ですよ。
これで実践編はマスター!ピカピカのマットレスで、今夜も気持ちよくおやすみくださいね。
掃除後のケアと予防法|ダニ・カビ・湿気を寄せつけない!

一生懸命マットレスをきれいにしたあと、大切なのが「その状態をキープすること」です。
湿気・カビ・ダニは、見えないうちにじわじわと増えていくもの。
でも心配しなくても大丈夫。ほんのちょっとの習慣と工夫で、清潔なマットレスを長く保つことができますよ♪
「面倒くさがりさん」でもできるやさしいお手入れ方法をご紹介します。
しっかり乾かすテク|陰干し・布団乾燥機・扇風機の活用法
湿気はカビの大好物。マットレス内部に湿気が残っていると、どんなにきれいに掃除しても再発してしまうことがあります。
お掃除後や、ちょっと汗をかいた夜の翌日などにできる効果的な乾かし方をまとめました。
- 基本は「陰干し」+「風」
マットレスは直射日光に弱い素材も多いため、日陰で風通しの良い場所で乾かすのがベスト。
室内なら窓を開けて、扇風機やサーキュレーターで風を当てるだけでもOKです。 - 布団乾燥機の活用
梅雨や冬のように湿気がこもりやすい季節には大活躍!
1回30〜60分ほどで、内部までじんわり乾かせます。
ダニ対策にも◎な高温モードがあれば、月1〜2回の使用がおすすめです。 - 立てかけ&裏面ケア
「つい裏面を忘れちゃう」という方、多いんです!
定期的にマットレスを立てかけて裏面も乾かすことで、湿気のたまりを防げます。
お天気のいい日はぜひ「ひっくり返す・立てかける」も取り入れてみてくださいね。
清潔を保つための習慣化アイデア|週1のプチ掃除でOK
毎日がんばらなくても大丈夫。週に1回の“ちょっとした習慣”を加えるだけで、マットレスの清潔度はぐんと上がります。
おすすめのプチ習慣はこちら♪
- 週1で「重曹パラパラ」+掃除機がけ
マットレス全体に軽く重曹をふりかけて15分放置 → 掃除機で吸うだけ!
消臭・湿気取り・皮脂対策に効果◎ - 寝具の見直し
シーツやパッドをこまめに交換・洗濯すると、マットレス自体が汚れにくくなります。
夏場は週1、冬場は2週に1回が理想的。 - 除湿シートを敷いて湿気予防
ベッドマットと床の間に「除湿マット」や「すのこベッド」を活用するだけで、通気性UP&カビ防止に!
「週1回の重曹タイム」「月1の乾燥タイム」など、自分に合ったペースで続けることが何より大切。
完璧じゃなくていいので、楽しみながら続けていけるといいですね。
ペットや子どもがいる家庭での安全対策&注意点
小さなお子さんやペットがいるおうちでは、安心して使えるかどうかも大切なポイント。
重曹は食品添加物としても使われるほど安全性が高いとはいえ、使い方にはちょっとした注意が必要です。
- 掃除中に舐めたり触れたりしないよう注意
お掃除中は、お子さんやペットの手が届かない場所で作業するのがおすすめ。
粉末が目や口に入ると刺激になることもあるので、必ず掃除機でしっかり吸い取るまで近づけないようにしましょう。 - アルコールや漂白剤との併用は慎重に
匂いが強いものや刺激のある成分は、呼吸器が敏感な子やペットに影響する可能性も。
基本的には重曹+水やお湯で十分なので、他の洗剤を使うときは換気をしっかり。 - マットレス周りのガード対策
おねしょや粗相のリスクがある場合は、防水パッドやシーツを必ず使いましょう。
こまめに洗えるカバーを併用すれば、マットレス本体まで汚れが届きにくくなります。
家族みんなが快適に過ごせるおうち環境をつくるためにも、「手軽・安全・ちょっとだけ手間」を意識してみてくださいね。
小さな積み重ねが、清潔で心地よい毎日につながりますよ。
マットレスを長持ちさせる!日常でできる清潔キープ術

一度きれいにしたマットレス、できればずっと清潔で気持ちよく使いたいですよね。
実は、ちょっとした工夫やアイテムの取り入れ方で、カビや汚れ、湿気からマットレスをしっかり守ることができるんです。
ここでは、「毎日がんばらなくても続けられる」マットレスの予防&ケア術を3つのポイントに分けてご紹介します。
防水シーツ・パッドの選び方&使い方
直接マットレスを汚さないための第一防衛ラインが、防水シーツやベッドパッド。
汚れや湿気をブロックしてくれるので、特にお子さんのいるご家庭や汗っかきさんには必須のアイテムです。
- 防水シーツの特徴
・裏側に防水加工が施されていて、おねしょ・寝汗・飲みこぼしをしっかりブロック。
・表面がゴワゴワしにくいパイル生地タイプが肌ざわりもよくて人気です。 - ベッドパッドの特徴
・クッション性をプラスして寝心地をやわらかく。
・通気性のある素材を選べば、湿気のたまりも軽減できます。 - 組み合わせのコツ
防水シーツ→パッド→ボックスシーツの順に重ねれば、汚れ・汗・摩耗のトリプルガードに。
汗をかきやすい季節は週1回の洗濯を目安にしておくと◎。
また、おねしょや生理中のトラブルが心配な方は、吸水量の多い防水パッドを選ぶとより安心ですよ。
頻繁に洗濯できない方は、替え用を2~3枚持っておくと便利です。
湿気・汚れを防ぐ寝具全体のケア|枕・布団・床の対策も
実は、マットレスだけをケアしても、他の寝具が不衛生だとニオイやカビが再発しやすくなることも。
「寝具全体で清潔空間をつくる」という意識が大切です。
- 枕・掛け布団
・汗や皮脂がたまりやすいので、カバーは週1回、季節の変わり目には本体も洗濯またはクリーニングへ。
・中綿の多い布団は天日干しや布団乾燥機でふんわり感を保ちましょう。 - ベッドの床・下部
・ベッド下はホコリが溜まりやすく、湿気がこもる場所。
・月1で掃除機+除湿剤設置を習慣にすると、カビリスクをぐんと減らせます。 - 部屋全体の湿度管理
・湿気が気になる季節は除湿機・サーキュレーターを活用して空気の流れをつくるのがおすすめ。
・湿度の目安は40〜60%。除湿器のタイマー機能を活用すると電気代も節約できますよ。
「シーツを干すついでに…」「掃除機ついでに…」くらいの気持ちで、寝具全体のケアも習慣にしていけるといいですね。
ひとつずつ、できるところからでOKです。
時短派におすすめ!除湿剤・消臭グッズの併用法
忙しくてなかなかお手入れの時間がとれない…という方には、「置いておくだけ」の時短アイテムも心強い味方。
最近では100円ショップやドラッグストアでも優秀な除湿・消臭グッズが手軽に手に入るので、ぜひ活用してみてくださいね。
- マットレス下に敷く除湿シート
・水分を吸収しやすい素材で作られており、たまった湿気を見える化できるタイプもあります。
・湿気の多い地域やフローリング直置きの方には特におすすめです。 - スプレータイプの消臭・除菌剤
・寝る前や朝起きたときにシュッと一吹きするだけで、ニオイの元をリセット。
・アルコール系、植物性など香りや成分は好みに合わせて選べます。 - 重曹×アロマの手作り消臭剤
・小瓶に重曹と数滴の精油(ラベンダーやティーツリーなど)を入れるだけで、おしゃれな自然派消臭剤に♪
・クローゼットやマットレス周りに置いてもOKです。
「とにかく手間なく、でも清潔に保ちたい」そんな方は、“置くだけ”グッズ+週1掃除のハイブリッドがぴったりです。
無理せず続けられる形で、自分らしいお手入れ習慣を見つけてみてくださいね。
それでもダメなら…買い替え検討のサインと判断基準

どんなに丁寧にお手入れしても、「もうこれは限界かも…」と感じる時がやってくることもあります。
マットレスは毎日使うものだからこそ、衛生面・快適性・安全性はしっかりキープしたいですよね。
ここでは、買い替えを検討すべきサインや判断基準を詳しくご紹介します。
「捨てるのはもったいないかも…」と迷っている方も、ぜひ参考にしてみてくださいね。
これが出たら注意!重度のカビ・変色・異臭の見極め方
目に見える汚れや変色がある場合、それが単なるシミなのか、衛生面で危険なレベルのカビなのかを見極めることが大切です。
以下のような症状が出ている場合は、マットレスの衛生レベルが低下しているサイン。
安全のためにも、思いきって買い替えを考えてみましょう。
- 黒や緑、赤っぽい点状の変色が広範囲にある
→ カビの可能性が非常に高く、特に黒カビは健康への影響も深刻です。
アレルギーや喘息などのリスクがある方は要注意。 - 洗っても消えない異臭がする
→ カビや雑菌がマットレスの内部まで繁殖している可能性大。
見た目がキレイでも、ニオイが落ちない場合は内部劣化が進んでいる証拠です。 - 表面が変色して黄ばみが濃く広がっている
→ 汗や皮脂が蓄積している状態。清掃しても改善しない場合は奥まで浸透していると考えられます。 - 触ると湿気っぽくジメジメしている
→ 通気性が損なわれ、常に内部が湿った状態になっていることも。
カビの再発リスクが非常に高くなります。
こうした症状が見られるマットレスは、一時的なお手入れでは対処しきれない状態であることが多いです。
特に小さなお子さんやご高齢の方が使う場合は、早めに買い替える方が安心です。
寿命の目安と買い替え時のチェックポイント
マットレスには寿命があります。見た目がきれいでも、内部の弾力や構造が劣化していると、睡眠の質や体への負担に影響を与えてしまうことも…。
以下のようなサインが出てきたら、「買い替えどき」かもしれません。
- 使い始めて7〜10年が経過している
・一般的に、マットレスの寿命は7〜10年が目安と言われています。
・ウレタンタイプは5〜8年、スプリングタイプは10年前後が多い傾向。 - 腰や背中が痛くなってきた
・寝起きに疲れが残る・体が重いと感じたら、マットレスのサポート力が落ちているかも。
・表面がフラットでも、内部がへたっていることがあります。 - 中央部分だけ沈み込みがある
・寝ている間に体重がかかる部分は、特に劣化が進みやすいです。
・「寝返りが打ちにくい」「同じ姿勢で固まる」などは寿命のサイン。 - バネや素材の音が気になる
・スプリング式の場合、「ギシギシ」と音が鳴るようになったら、内部の構造が不安定になっている証拠です。 - 衛生面が心配で安心して眠れない
・お手入れしても不安が残る場合は、気持ち的にも買い替えのタイミングかもしれません。
寝具は体と心の健康に直結するアイテムだからこそ、「不快感がある=替え時の合図」と考えるのがおすすめです。
新しいマットレスに替えることで、睡眠の質が大きく変わることもありますよ。
最近は「高反発・低反発・通気性・除菌加工」など、選択肢も豊富。
お部屋の環境や体の悩みに合ったマットレスを選び直して、毎日の眠りをもっと快適にしていきましょうね。
まとめ|重曹掃除でマットレスがよみがえる!快眠を手に入れよう

「マットレスっておうちで掃除できるんだ…!」と驚かれた方も多いかもしれません。
実は、重曹という身近なアイテムひとつで、気になる汚れ・臭い・湿気をしっかりケアできるんです。
今回ご紹介した内容は、専門的な知識がなくても、どなたでもできるお掃除方法ばかり。
最初は少し手間に感じるかもしれませんが、清潔な寝具でぐっすり眠れた朝の気持ちよさを体験すると、きっと「やってよかった♡」と思えるはずです。
実践できることから今日スタート|やるべき順番おさらい
では最後に、この記事でご紹介した「マットレス重曹ケア」の流れをもう一度おさらいしてみましょう。
- マットレスの素材を確認
ウレタン・コイル・ラテックス…素材によってできるお手入れ方法が違うので、まずは「うちのマットレスは何製?」をチェック。 - 必要な道具を準備
重曹・古タオル・掃除機・スプレーボトルなど、あるものでOK♪
換気や防水シートの準備も忘れずに。 - 重曹をふりかけて、放置→掃除機で吸い取る
汚れの程度に合わせて、ペーストやスプレーを使い分けましょう。
おねしょ・血液・皮脂など、汚れ別の対応方法もぜひ活用してみてください。 - しっかり乾燥&予防策を取り入れる
陰干し・布団乾燥機・除湿シートなどを使って、湿気をためない工夫が大切です。 - 週1回の軽いお掃除で清潔をキープ
忙しい方も「重曹を振って掃除機で吸うだけ」でも十分!
お掃除は無理のない範囲で、楽しみながら続けていきましょう。
どれか一つでも、「これならできそう♪」と思えたら、ぜひ今日から取り入れてみてくださいね。
気になる部分だけでも、こまめにお手入れをすることで、マットレスの清潔度と快適さは大きく変わってきますよ。
気になる人はプロのクリーニングや防ダニ加工も検討しよう
「どうしても落ちない汚れがある…」「重曹では取りきれなかった…」という場合は、無理をせずプロにお願いするのもひとつの手です。
最近では、自宅まで取りに来てくれる「宅配クリーニングサービス」や、防ダニ・抗菌・抗ウイルス加工を施してくれる専門業者も増えてきています。
- プロのクリーニングが向いているケース
・広範囲にカビや黄ばみが広がっている
・ニオイが強く、何度掃除しても取れない
・高価なマットレスを長持ちさせたい場合 - 費用の目安
・シングルサイズ:約8,000〜15,000円前後が相場。
・防ダニ加工や抗菌コートを含めると、追加で数千円かかる場合も。
「まだ使えるけど衛生面が不安…」という方にも、プロの技術は頼もしい味方。
必ずしも“買い替え”ではなく、“クリーニング+予防加工”で再スタートできる場合もあります。
大切なのは、安心して眠れる環境をつくること。
お掃除もクリーニングも、“自分と家族の健康を守るためのケア”として、気持ちよく取り入れていきたいですね。
この記事が、あなたの「マットレスとの上手なつきあい方」のヒントになればうれしいです♡
さあ、今日からちょっとだけ、寝具のことに目を向けてみませんか?
心地よい眠りは、明日の元気を育ててくれますよ。